楽天ペイで決済。松屋の朝定食で、楽天ポイントを取得する。QR決済方法とは?
kenta1118
kenta1118のブログ
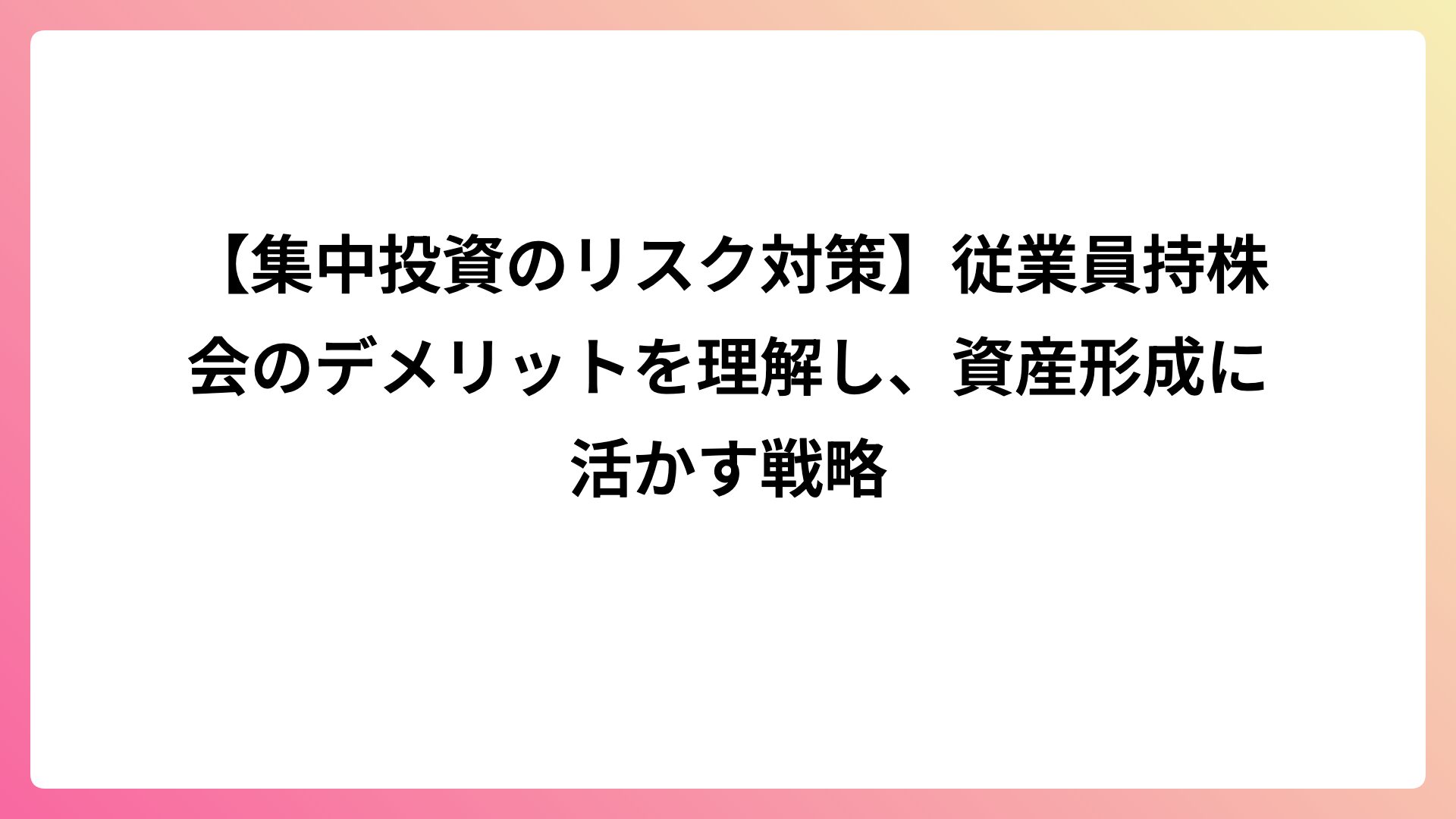
ご自身が働く会社に「従業員持株会」という制度はありますか?
毎月の積立金に対し、会社が5%の補助金を上乗せしてくれるなど、非常に魅力的な福利厚生制度ですが、投資の専門家からは「集中投資」になるため危険だと批判されることもあります。
この記事では、持株会が抱える集中投資のリスクを明確にしながら、そのデメリットを上回るメリットの活用法、そして老後資金に備えるための分散投資を組み合わせた総合的な資産形成戦略を解説します。
経済学者や投資の神様ウォーレン・バフェット氏など、投資のプロの意見をまとめると、持株会は「投資の大原則」に逆行するため、否定的な意見が多いのが事実です。
しかし、この集中投資のリスクを理解した上で、持株会を「優良な資産形成ツール」として活用する方法があります。
私が長年持株会を続けているのは、集中投資というデメリットを上回る、以下の強力なメリットがあるからです。
月の積立金に対し、会社から5%の補助金(奨励金)が上乗せされることが最大のメリットです。これは、他の投資ではなかなか得られない、確実な初期リターンとなります。
同僚の失敗談から、持株会特有のルールを理解することが重要です。
| 失敗例 | 鉄則(ルール) |
|---|---|
| 「リアルタイムで売り買いできる!」と勘違い | 鉄則: 持株会の『売り』『買い』はリアルタイムではできない。払い出しには数ヶ月かかるため、投機(ギャンブル)的な運用はしない。 |
| 高値で申請したが株価が下落して大損 | 鉄則: 持株会は「ドル・コスト平均法」による長期積立に徹する。 |
持株会での集中投資は否定できません。だからこそ、老後の不安を解消するためには、他の分散投資と組み合わせることが必須です。
筆者も、持株会は継続しつつも、集中投資とならないように、以下の資産形成を並行して行っています。
退職金もあてにならない時代、自分で老後資金を構築することは急務です。「先手必勝!」で、持株会のメリットを最大限に活かしつつ、他で分散投資を行うのが最強の戦略です。
以上、参考になれば嬉しいです。
分散投資で、今日も一日お元気で…
