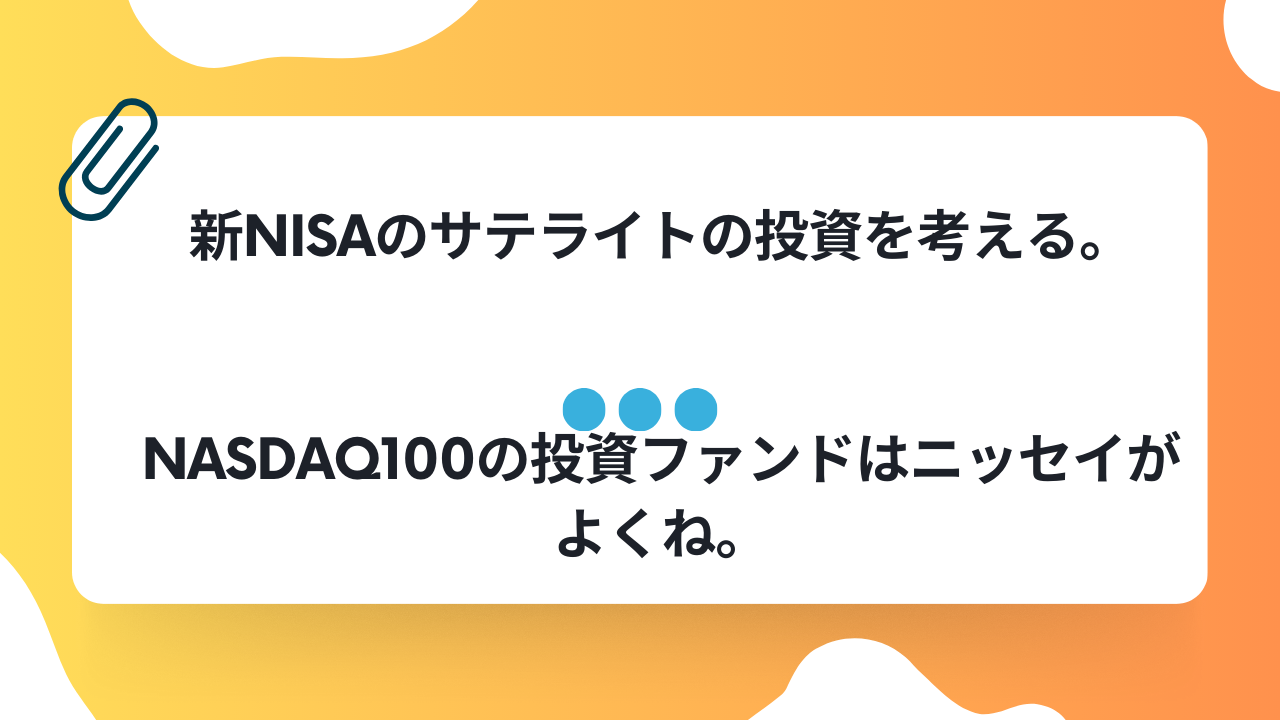太陽光発電を卒FITして5年が経過。対策を考える!
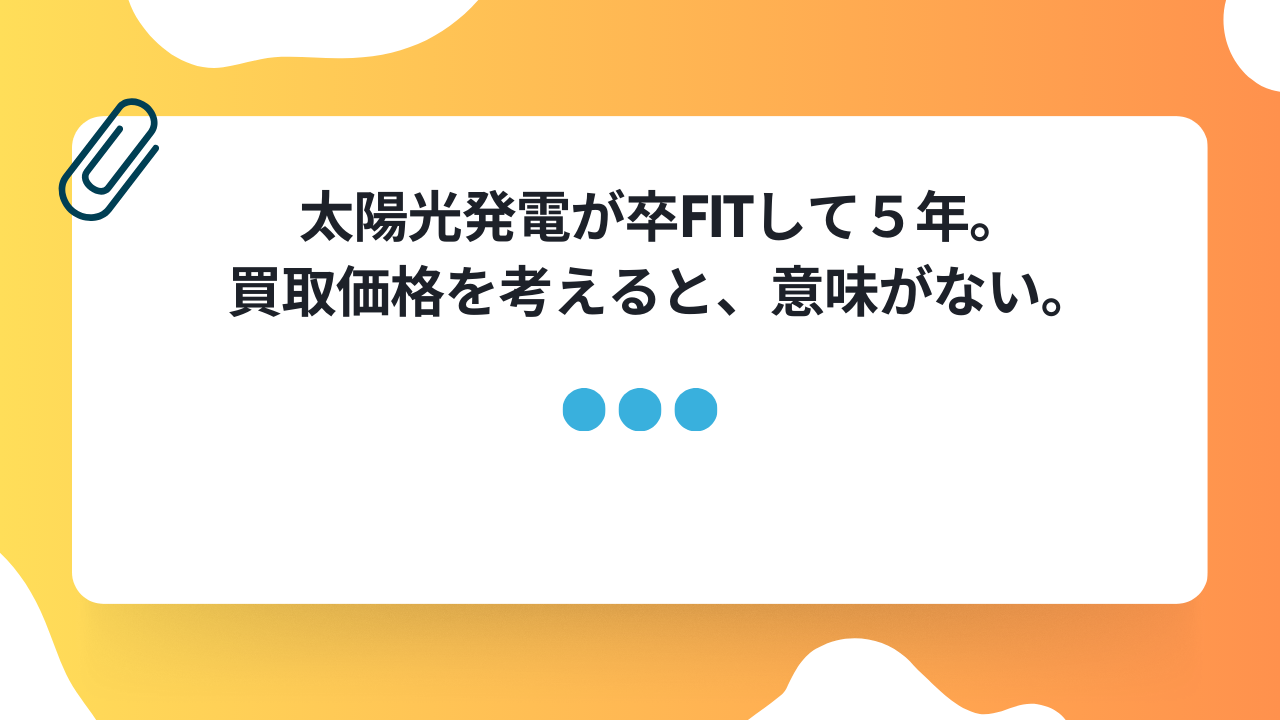
太陽光発電を導入して、はや15年…(汗)
屋根には、ソーラーパネルが所狭しと載っています。
しかも、卒FITして5年が過ぎようとしている現状。
何かしないと、雀の涙ほどの買取価格で電力会社に卸すことになり、一時期の売電意欲も無くなりました(涙)
今回は、卒FITしたことについて考えてみたいと思います。
はじめに、卒FITとは
FIT(Feed-in Tariff)制度は、日本の再生可能エネルギーの普及を促進するために導入された固定価格買取制度です。
この制度は、再生可能エネルギーによって発電された電力を一定期間、固定価格で電力会社が買い取ることを保証するものです。
しかし、FITの買取期間が終了した後の状況については、「卒FIT」と呼ばれています。
卒FITの背景
日本では、2009年11月に余剰電力買取制度(FITになる前の制度)が導入されました。
この制度により、太陽光、風力、水力、バイオマスなどの再生可能エネルギーによる発電が大幅に増加しました。
特に、太陽光発電は多くの家庭や企業に普及しました。
しかし、FIT制度の買取期間は通常10年間と定められており、2022年頃からこの期間が終了する発電施設が増え始めています。
これが「卒FIT」の現象です。
卒FIT後の選択肢
卒FITを迎えた発電事業者や家庭は、以下のような選択肢があります:
- 新しい買取契約を結ぶ:
一部の電力会社や新電力(新規参入電力事業者)が、卒FIT後の電力を買い取るサービスを提供しています。ただし、FIT期間中の買取価格に比べて低価格になることが一般的です。 - 自家消費に転換する:
発電した電力を自らの施設や家庭で使用する方法です。これにより、電気代の削減が期待できます。また、余剰電力を蓄電池に貯めて、必要な時に使用することも可能です。 - 新しいビジネスモデルの検討:
地域エネルギー会社との共同事業や、エネルギーシェアリングなど、新たなビジネスモデルを模索することも考えられます。
現状
現在、❶新しい買取契約を結ぶ…というか、更新されたような状態で買取価格は雀の涙。
無償で提供まではしたくはないので、我慢しているのが現状。
卒FITの課題と展望
卒FITを迎えることで、以下のような課題が浮上します:
- 買取価格の低下:
新しい買取契約の価格がFIT期間中の価格に比べて低いため、発電事業者の収益が減少します。 - インフラの老朽化:
初期に設置された発電設備の老朽化が進み、維持・管理コストが増加する可能性があります。
一方で、卒FITは新たなエネルギー利用の形態を模索する好機でもあります。
再生可能エネルギーの自家消費の推進や、地域エネルギーの活用によって、持続可能なエネルギー社会の構築が期待されています。
まとめ
卒FITは、日本の再生可能エネルギー普及の新たなステージを迎える重要な転機です。
買取価格の低下や設備の老朽化といった課題に直面しながらも、自家消費の推進や新たなビジネスモデルの模索を通じて、持続可能なエネルギー社会を実現するための大きな一歩となるでしょう。
さて、5年もの放置期間を経て結論を出していきたいと思います。
今回は、卒FITを迎えたことについて考えてみました。
以上、参考になれば嬉しいです。
それでは今日も一日お元気で…